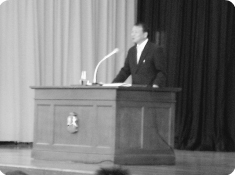|
「百年の歴史」記念講話から
|
|
百年誌監修者 半 田 和 彦
|
明治以前、日本に生産・技術の概念はなく職人の経験・習練に裏付けられた“わざ”“すべ”としての技芸・芸術であった。その意味で日本の技術は工芸的性格が濃いと言える。
○官営模範工場作られる。
明治政府は西欧諸国の近代産業を背景とした圧倒的国力に急ぎ追いつくため農民から徴収した地租を基礎財源として国家による近代的工場(官営工場)の建設を行った。そのため機械は外国製で技術指導者は御抱技師と呼ばれた外国人達であった。
○官営工場の民間への払い下げ
多額の国税を投入して作った官営工場は明治14年頃から有力商人に安く払い下げられ、彼らは政商と呼ばれ、戦前の大資本家成立の起源となった。産業界は政府の手厚い保護を受けて成長したため労働者への低賃金と長時間労働のため国内の購売力不足から軍事力を背景に隣国への侵略政策となってしまった。
日清戦争後、工業立国への機運が高まり学校教育の果す役割が大きいとの認識から実業学校の必要が高まり明治33年の県会で19名の議員の賛成で工業学校設立の調査案が可決され、秋田市、能代、土崎の地区からの熱心な誘致運動の末に金砂町7町歩に秋田工業が作られることになった。
○初代校長の理念
初代中村校長は「現在の工業製品の進歩は主として製作の正確さにある。工業用機械の耐久性は短かくないから工業上精密で高度なものを学校に購入しようと思う。だから、いたずらに外国製の購入を避けたり、国内の機械を単に安いからとの理由で選ぶのは愚行に等しい。学校教育者の立場から精密で優秀なものを生徒に用意すべきである」と県に主張している。このような理念が工業高校を永く支え、今日のような伝統高校を作りあげたと言えるだろう。